投稿・コラム
職業紹介事業の実施要領
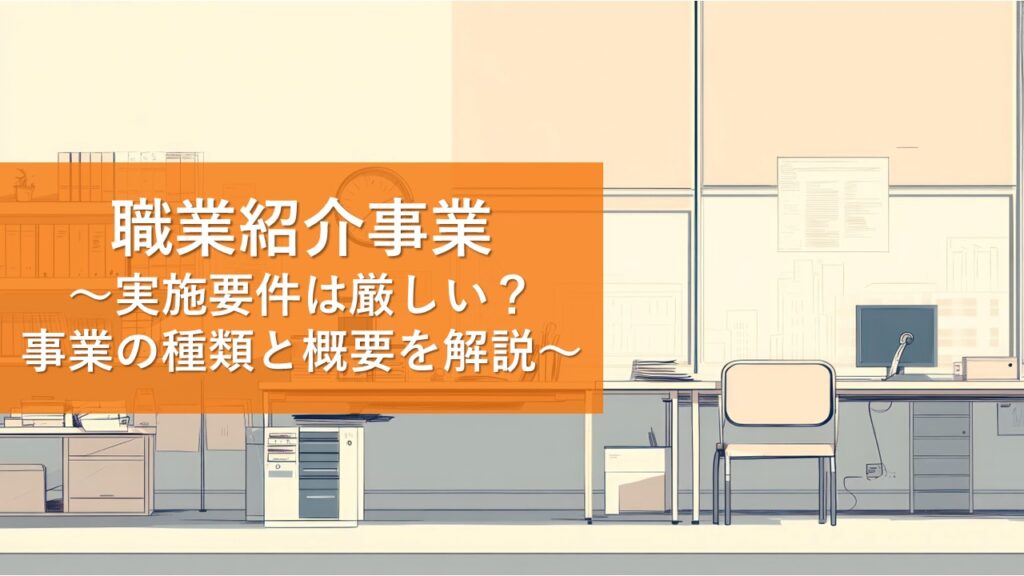
はじめに
職業安定法は、労働力不足のためにその需要と供給の調整を図ること並びに各人の能力に応じて妥当な条件の下に適当な職業に就く機会を与え、職業の安定を図ることを目的として制定されたものです(法1条)。
本稿では、求職者が利用する職業紹介事業に関する規制についてご紹介致します。
職業紹介とは
そもそも「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせん(紹介)することをいいます。分かり易く言うと、仕事を探す人と働き手を探すもの(人・企業)との間をとりもち、両者を結びつけるもののことをいいます。
したがって、職業紹介事業とは、このように求人者と求職者とを結びつけることを業とする事業者のことをいいます(厚生労働省HP参照)。
あっせんとは
「あっせん」とは、求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために、両者の間をとりもち、引き合わせることをいいますが、この「あっせん」行為は広く解され、上記行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨する、いわゆるスカウト行為も含まれると考えられています(最判平成6・4・22 民集 第48巻3号944頁)。
職業紹介事業の種類
職業紹介事業には、大きく分けて有料のものと無料のものの2種類に分けることができますが、具体的には、次の事業を挙げることができます。
1.特定地方公共団体(※)の行う無料職業紹介事業
2.有料職業紹介事業
3.無料職業紹介事業
4.学校等の行う無料職業紹介事業
5.特別の法人の行う無料職業紹介事業
※特定地方公共団体とは、職業安定法29条1項に定める無料の職業紹介事業を行う地方公共団体のことをいいます。
職業紹介事業の実施要件
上記に挙げた各職業紹介事業を実施するためには以下の手続きが必要となります。
特定地方公共団体の行う無料職業紹介事業
地方公共団体は、厚生労働大臣へ通知を行うことにより当該事業を行うことができます。
「通知」だけでよいため、他の事業よりも要件が緩やかといえます。これは自治体が主体であり、その公共的中立的性格から求職者より不当な手数料をとる等、中間搾取のおそれがないと考えられるからでしょう。そのため、有効期間の定めはありません。
なお、地方公共団体は、有料の職業紹介事業を行うことはできません。
有料職業紹介事業
厚生労働大臣の許可
有料の職業紹介事業を行うためには、厚生労働大臣の許可が必要となります。
厚生労働大臣の許可は、その裁量によるのではなく、予め労働政策審議会の意見を聴いて許否を判断することになります。
許可(原則禁止という判断が前提にあります)という厳格な要件が設けられているのは、先の地方公共団体が職業紹介事業を無料で行うのとは異なり、求人者が求職者から不当に手数料を徴収するなどして中間搾取が行われることを事前に防止する点にその趣旨があります。
欠格要件
許可の欠格要件も定められており、次のいずれかに該当する場合には許可がおりません(法32条)。
1.禁固以上の刑に処せられ、又は職業安定法その他政令で定める法律等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2.心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
4.職業紹介事業の許可が取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
5.暴力団員等がその事業活動を支配する者 等
要するに、これら欠格要件を持つ者は、求職者や求人者の利益を害するおそれが高く、有料の職業紹介事業として適格性を欠くため、許可が下りないということです。
取扱職業の制限
有料の職業紹介事業は、中間搾取を防止する観点から、求職者に以下の職業を紹介することはできません。
1.港湾運送業務
2.建設業務
なお、上記のほか、その職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業も禁止されることとなりますが、現在厚生労働省令で規制されている職業はありません。
職業紹介責任者とは
有料の職業紹介事業者は、その事業規模を問わず、職業紹介に関し所定の事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、許可の欠格事由に該当しない者のうちから職業紹介責任者を選任しなければなりません(法32条の14)。
職業紹介者の統括管理する事項として次のものが挙げられます。
1.求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること
2.求人者の情報及び求職者の個人情報の管理に関すること
3.求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の運営及び改善に関すること
4.職業安定機関との連絡調整に関すること
有料職業紹介に係る手数料
有料の職業紹介事業においては、一部の例外(芸能関係、モデル業など)を除き原則として求人者からのみ手数料を徴収し、求職者から手数料を徴収することは認められていません。
手数料を徴収する場合には、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づき徴収することが必要とされるなど、手数料の報酬にも一定の実施要件が定められています。
無料職業紹介事業
無料の職業紹介事業を行うためには、学校や特別の法人が行う無料職業紹介事業を除き、厚生労働大臣の許可が必要となります。
また、厚生労働大臣が許可を行う際には、労働組合に対する場合を除いて、予め労働政策審議会の意見を聴かなければならず、要件は厳格に定められています(法33条1項)。
なお、無料の職業紹介事業においては、有料の職業紹介事業と異なり、取扱職業の範囲に限定はありません。
学校等の行う無料職業紹介事業
小学校及び幼稚園を除く学校、専修学校、職業能力開発校等、職業能力開発大学校の施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該学校等の学生生徒等(限定)について、無料の職業紹介事業を行うことができます。
上記学校等であれば求職者である学生生徒等からの中間搾取の恐れが小さいと考えられるため、厚生労働大臣への届出のみで足りるとされています。
特別の法人等が行う無料職業紹介事業
特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の構成員(限定)を求人者とし、又は当該法人の構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができます(法33条の3第1項)。
特別の法律によって設立された法人とは、次のものが挙げられます。
1.商工会議所
2.商工会
3.農業協同組合など
特別の法人等が行う無料職業紹介事業においても、求職者への中間搾取の恐れが少ないことから厚生労働大臣への届出のみで足りるとされています。
福岡の顧問弁護士をご検討の方へ
本稿では、職業紹介事業の概要とその実施要件についてご紹介致しました。
本稿でも紹介したように、職業紹介事業については、その沿革から求職者に対する中間搾取が行われていたことから、実施要件が厳格に定められています。
職業紹介事業をはじめ、各事業の実施には所定の実施要件を満たす必要がありますが、迅速・適切に手続を履践し、計画通りに事業を開始するためには、各事業に適用される法律に精通した専門家の助言を聞きながら進める方が安全・確実です。
また、顧問弁護士であれば、事業開始後も必要に応じて、最新の法令に準拠した適切・迅速な助言を受けることができます。
弁護士法人いかり法律事務所には企業法務に精通した弁護士が在籍していますので、福岡で顧問弁護士をご検討、お探しの方は、ぜひ当法律事務所までお問い合わせ下さい。